
「破壊せよ、とアイラーは言った」という中上健次の本がありました。また、「ジャズと自由は手を繋いで行く」という時代がありました。確かにジャズはアメリカ黒人の差別撤廃の動きと連動しているように見えました。東京オリンピック(1964年)で、優勝したアメリカ黒人選手が表彰台で星条旗に拳を振り上げ、うつむいていたのをよく覚えています。アメリカでフリージャズが盛んになり始める時期でした。
日本でも、権力・権威を否定するという意味でフリージャズが象徴的に扱われていました。たしかに甘ったるい音楽ではなく、強く刺激的な音でなければ、権威の否定はできないと考えるのは自然です。「嘆き」ではなく「叫び」。溜まった鬱憤を晴らすためにも「行け,行け、最後まで行け-!」という気分があったのでしょう。
アイラーが亡くなったのが三島由紀夫の自決と同時期でした。時代の雰囲気が伝わります。アイラーは亡くなる前、どんどんゴスペル音楽やロックに接近していました。アイラーの音楽は「破壊せよ」とも「創造せよ」とも言ってないのです。自らのルーツや、世の中の流れに興味を持ち演奏したいように演奏をしたわけです。
ナチの強制収容所で音楽がナチのためにも使われた、ということで「音楽への憎しみ」を書いたパスカル・キニャール。正反対の目的のためにも同じ音楽を使うことができます。「夜と霧」の映像が、反ナチにも、親ナチにも使えるのと同じかもしれません。
アイラー亡き後、中上さんはボブ・マーリーやサムルノリに熱中していたようです。それも象徴的です。反戦フォークを歌っていた人たちが芸能界に入り成功するというのも寂しい話です。
(一方、西洋音楽史でのバロック・ロマン・近代音楽・現代音楽という流れが、そのままジャズ史に凝縮して顕れているという指摘もあります。モダンジャズで複雑になりすぎた和音に対してモードになったり、フリーになったり,偶然性を使ったり、民族性を使ったりという傾向がそのままある。フリージャズも音楽に置ける自然な展開だったのかもしれません。)
60年安保、70年安保、成田空港などの闘争があり、新宿は熱く、フリージャズが多くの聴衆を得て、連動して語られました。日本の即興シーンにはその流れが色濃くあります。しかし、ヨーロッパでは、インプロヴァイズド・ミュージックと、フリージャズは分別され、お互いが誇りを持っているように感じます。
叫び・情念的な演奏に惹かれる理由はいくつか考えられます。「良い格好つけの否定」「肉体の限界のウソのなさ」「カタルシスを共有する祭り的ドラマトゥルギー」「悪・腐に対する無意識の憧れ」「やけくその突発的エネルギーの異常な高さ」「抑えられた破壊欲望」などなどが浮かびます。
「日本人の即興演奏家に共通するものを感じる」として吉澤元治にも灰野敬二にも今井和雄にも齋藤徹にも同じものが見えると言われたときには正直驚きました。吉澤さん灰野さんには全く相容れないものを感じていたからです。そういう意見は謙虚に考えて見たいと思っています。
叫びや情念的な演奏では、自分の身体的・精神的限界を超えることはできません。自分を越えることを目指していると、それは足かせになります。選ばれた人のみが許される行為のようさえ見えます。
自分のできないことを代わりにやってくれるという期待と共感から熱心なファンが生まれ、演奏家の伝説・エピソードが語り継がれていきます。
喜怒哀楽から自由になれないという側面もあるようです。正しさに囚われてしまい、選択肢が減っていくのです。正しさは創造とは関係のない次元の話です。
日本の伝統音楽でも、鬼気迫った(常軌を逸したと言っても良い)演奏があり、尊ばれてきました。どこかで「もの狂い」への憧れがあり、そこともどこかでつながるかもしれません。
身体性に任せきってしまうことを止めるということは、知的に偏りがちになります。アコースティック楽器によりインプロビゼーションは、身体性を保ち、かつ、客観性も保つことができるという利点があります。が、いずれにせよ綱渡りです。
逆に電気機材を使うインプロビゼーションは、仮想の身体性を組み込む必要があります。ツマミを回しペダルを踏むだけで音量や音質が変わるのだから、ツマミ回しに、ペダル踏みに、アコースティック楽器での音量・音質変化と同じ質量をシミュレートできるかが大事になります。
更に言えば、身体そのもののダンサーは、アコースティック楽器の自在さもありません。しかし、弱点を利点に逆転することこそが人の知恵なのです。その振れ幅が大きければ大きいほど良いとさえ言えます。1㎝の身体の動きの中に無限の動きを表すことができるのです。
時代の限界、身体の限界、精神の限界など限界だらけのなかでは、もっともっと確信犯にならねばなりません。

「即興」の対義語は何でしょう?普通思い浮かべるのは「作品」ですね。それは間違ってはいないけれど、充分ではない。大きく捉えてみれば、即興の対義語は「常識」・「当たり前」ではないでしょうか。さらにいえば、「自分自身」と言い換えることができると思います。
発見があるかどうか、がカギです。何も用意していなくても垢のついたような手癖を演奏していたら、発見はありません。それは、即興ではない。逆も真なり、全てを書いてある譜面を演奏しても即興はある、ということを以前書きました。
大きく捉える(それ自体が即興かもしれませんね。)と、いろいろなことが見えてきます。怒濤のようなグローバリゼーション,商業主義。テレビ、マスコミ、広告を疑う、ものを大事に使う、むやみに買わない、直す、作ってみる、歩いてみる、等々。自分の目で見て、自分の耳で聞いて、自分の足で歩いて、自分の頭で考える、その瞬間瞬間に創造があり、即興があるのではないでしょうか。洗濯物を干すときに、この靴下の隣にこのタオルを干すと良い感じになる、それで良いのです。
「効果」を疑う、これも大事です。ちょっと過激に言えば「効果は本質を殺す」のではないでしょうか。効果的であること、能率的であること、に異議を差し挟む人は、この忙しい世の中、あまりいない。さて、即興の出番です。「本当にそう?」と問う瞬間の発見。同じように「好き・嫌い」を疑ってみることも必要です。本当に「好き」なのか?本当に「嫌い」なのか?
効果は、どうしても「もっともっと」を目指します。より効果的に、と努力している内に、何を失うか?それは本質なのかもしれません。こうやると「カッコイイ」を疑う、あえてやらない。音が小さくて聞こえない時、聞こえるように音を拡声するのではなく、耳をそばだてて聴く方向に持って行く。
良い音、キレイな音、美しい音を出すことに、ちょっと待った、を言う。不可能なことを演奏する。これが即興の役目でしょう。
効果的な音を味わってスッキリとする=日常を忘れる、のではなく、何かわからないけれど、曰く言い難いものを思い出してワクワク・ドキドキ・ドギマギする。その方が大事でしょう。そのきっかけに即興は役に立つのです。
それは、アマノジャクかもしれません。面白いものに対して、人はどんどんと興味を持ち、時間を忘れて没頭します。それが発明につながったり、創造につながったり。「面白い、面白い」を続けていくと、行き着く先に原水爆の発明があったり、クローン人間があったりするのも現実です。確かに今流行りのゲームは面白いらしい、けれど、面白い面白いと刺激をされ続けていって、精神を破壊されてしまう人も出てきているわけです。
「学ぶ」ことは「まねる」ことから始まっているし、最近取りざたされているミラー・ニューロンは人の本質です。真似から始まることは確かです。しかし、その暴走に待ったを掛ける必要がある。「だって、しょうがないじゃない」となかなか言わないアマノジャクが必要なのです。その時にインプロビゼーションが肯定的に役に立つのです。

室岡一さんが録音した「胎内血流音」というものがあります。学生時代、おもしろくてヒーヒー言いながら読んだ中公新書「胎児の世界」(三木成夫著)に出てきて、探し求めました。泣き止まない赤ん坊対策に効果的ということで販売されていました。
いやはやもの凄いノイズです。胎児の大きさを考えると,全身でこの音を10ヶ月聴いていたと思うと想像を越えていますが、人種も民族も関係なしに人類全員がこの経験を持っているわけです。だから、赤ん坊が安心して泣き止むのです。究極の安心がこのノイズであることは人間が生物の1つとして,巨大な何かの一部であることを物語っている気がします。ありったけの喜怒哀楽の叫びも、殺すな!の悲鳴も、歓喜の歌も無にしてしまうこの大音量ノイズ。
ロックやクラブの大音量は、このノイズを無意識に模しているのかもしれません。ロックギターの代表的なイフェクターはディストーションといって音を歪ませる装置であることも無関係ではないでしょう。会場・ライブハウスを子宮にする。
ノイズは即興において、大変重要なファクターです。
ノイズは2種類に分けられます。1つはエンジンやモーターなどの回転から派生するもの、1つは自然の素材の中に含まれているもの。人の記憶を呼び覚ますものは後者であると思います。
回転に基づくノイズは規則的です。胎児の心音が規則的過ぎる場合、病気の可能性が高いというのも示唆的です。生命はノイジーで不規則、乱調にこそ宿るということでしょう。
ここでジャック・アタリとニコラウス・アーノンクールの引用をします。(ちょっと訳が回りくどくてわかりにくいですが、本文を忠実に訳したかったのでしょう。)ミッテラン大統領の補佐官だったアタリのこの本のタイトルはまさに「ノイズ」(なぜか日本版は『音楽・貨幣・雑音』)
「西洋の知は,この25世紀というもの世界を見ることに汲々としてきた。それは、世界が見取られるものではなく、聞こえてくるものだと言うことを理解しなかった。世界は読み取られるもので拍、聴き取られるものなのだ。
科学はいつでも感性を監視し、手なずけ、抽象化し、去勢しようとしてきた。生とは騒々しいものであり、ただ死だけが静寂であることを忘れて。労働の雑音(つちおと)、人間の雑音(ざわめき)、自然の雑音(ものおと)、買われ、売られ、あるいは禁じられる雑音(おと)、雑音の聞こえぬ所に、何も起こりはしない。
今や、眼差しは破産した。われわれの未来を見ることができずに、ただ、抽象、無意味そして沈黙からなる現在を作りだしてしまった眼差しは。今や、社会を、その統計に依ってではなく、その雑音、その芸術、そしてその祭りによって見きわめることをまなばなければならない。雑音を聞くことによって、人間の、そして数字の狂気が我々を何処へ導いていくのか、さらに、今なお可能な希望とは如何なるものかが、よりよく了解されえるであろう。」(「音楽・貨幣・雑音」みすず書房 ジャック・アタリ著・金塚貞文訳)
ヨーロッパ貴族の血筋を引くアーノンクールは、古楽の研究を続け、ウイーンフィルのニューイヤーを指揮したりして、まさに「ヨーロッパ音楽」の中心にいます。その人がこう言っています。
「音楽がもはや人生の中心に存在しなくなってから、全てが変わった。装飾としての音楽はまず第一に〈美しく〉あらねばならない。音楽はけっしてわずらわしくてはならないし、人間を驚かしてもならないのである。現代音楽はもはやこうした要求を満たすことはない。なざならそれは、あらゆる芸術と同様、すくなくともその時代、つまり現代の精神的状況を反映しているからである。しかしわれわれの精神的状況の誠実で仮借ない批判は、ただ美しいだけではありえない。それはわれわれの人生をえぐり出す、つまり煩わしいものとなる。こうして人々は、それが煩わしい、あるいは場合によっては煩わしくあらねばならぬという理由で現代の音楽から遠ざかるという、矛盾に満ちた状況が生じた。・・・
〈美しさ〉とは,あらゆる音楽のもつひとつの構成要素である。われわれは他の構成要素を無視する場合にかぎって、美を特定の判断の基準として用いることができる。われわれが音楽を全体としてはもはや理解することができなくなって、いやもしかしたらもはや理解しようと望まなくなって、はじめて音楽をその美しさにまで引き下ろし、いわばアイロンで平らに引き延ばしてしまうことが可能となったのである。」(音楽之友社「古楽とは何かー言語としての音楽」アーノンクール著 樋口隆一・許光俊訳)
我らがアジアの先哲の意見を、岩波講座「日本の音楽・アジアの音楽6」笠原潔「中国古代の音楽思想」論文から引用します。
荘子・天地篇「冥冥の中に独り暁を見、無声の中に独り和を聴く」(盛徳の人は、暗闇のなかに暁を視、音無きところに楽の和を聴き取る)
孔子・間居篇「無声の楽(音を発しない楽)こそ究極の楽である」
荘子・斉物論篇「〈人籟〉とは人が笛を吹いて出す響き(音楽)、〈地籟〉とは風が木の虚ろに吹きつけてたてる響き(自然の音響)である」〈天籟〉とは、「人籟にせよ、地籟にせよ、空気の吹きつけ方は異なるが、穴が音を立てるという点では皆同じである。音を立てるものは穴であるが、その穴に音をたてさせているものは誰だろうか」
「人籟を聴くとは笛の音に耳を傾けること、地籟を聴くとは自然の音響に耳を傾けることを言うとすれば、天籟を聴くとは、人籟を人籟として成り立たせているもの、地籟を地籟として成り立たせているもの、に耳を傾けることを言う、すなわち人籟・地籟の区別を越えて、それらの背後にある根源的な存在に耳を傾けることを言う」

「聴くこと」は「待つこと」であり「信じること」
即興演奏に関わらず、人生一般に言えることで、いつも思い出すようにしている言葉です。立ち止まらずに視ることはできます。が、聴くためには立ち止まらなければなりません。立ち止まるためには信じていないと立ち止まれません。野口三千三さんは「貞く」と書いて「きく」と読ませて、「野口体操・からだに貞く」「野口体操・おもさに貞く」という2冊の本を書きました。日本では、香りも「きく」、酒も「きく」わけですので、「きく」ことはいろいろと拡がりを持ちます。シェークスピアも「目じゃない、耳でみるんだ」と書いています。
即興演奏の現場から体験できます。
「信じて」「待って」いる、そうすると共演者に自分の演奏を「してもらう」ことさえできます。自分の良いところを表現して勝ち負けを競うわけではない。せっかく一緒に同じ場所にいて音を出しているのだから、そうしたいものです。共演者をそして自分を信じることができず待てないと共演は成り立たない、演奏は成り立たないわけです。
音楽を破壊するのではなく、音が音楽になる直前の状態を味わいたいと思っています。ノイズや音の断片から歌になる直前を味わいたい。そのためには、変な言い方ですが、ある程度のところで歌にしてしまわずに、「まだまだ」とギリギリまで待つのです。
フリージャズの現場では、何も無しで始まっても、ある音程とかあるリズムある音楽に共有意識が生まれると、そのまま「音楽」にしてしまうことがよくあります。この方法だと、自分の知識・情報・技術を越えたものが出にくい。
インプロバイズドの現場でも「待ち」きれずに、似たようなことが起こることがあります。大事なのはどの方向を向いているかかです。太田省吾さんから学んだことの中でいつも思い出すのは、「喜怒哀楽は表現ではない」ということと「否定の文脈で語ることは簡単、これから大事なのは肯定の文脈で語ることだ」ということです。
インプロビゼーションも否定でなく、肯定の文脈で捉えることが大事だと思います。信じるために疑う、とでも言うように。
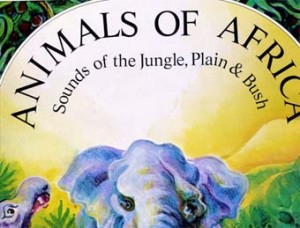
私の関係したCDの中でジャバラレコードの「アウセンシャス」というピアソラ集は、一定期間キングレコードが出したりして、ともかく1番売れました。一方、即興関係のCDは狭い居住空間を圧迫し続けています。CDには、商品という側面と作品という側面があります。横尾忠則さんは、イラストレーターから芸術家に変わったと言っています。注文があってはじめて成り立つイラストから、作品として自立している芸術作品へ。
「即興演奏のプロって何なのだろう?面倒だからやめようか?」とミッシェル・ドネダと話題になります。何でも商品価値にしてしまう現在、ミッシェルの息音でも、私の横弾きでも商品として交換されます。まあ、そうしないと生活できないということも確実にあります。そうしなくても生活できないというのが実態ですが。
即興は、そのあたりにも、疑問を投げかけています。誰でもできること、年齢差・経験差・習熟度差・性差・民族差何もないところが大きな利点です。5分間くらいの演奏ならば、楽器のことを知らない人のほうが、私より面白いかもしれません。
長岡鉄男さんが取り上げるLPはとても刺激になりました。高柳昌行さんと競って買い求めたのも良い想い出です。滅多にお目にかかることができないような、尖った現代音楽から古楽、民族音楽など本当に差別無なく扱い、情報の少ない当時、コントラバスのLPの紹介はありがたいものでした。かれは所謂オーディオ評論家です。良い音の録音を探し続けているとこういう良い音楽に出会うと言っていました。私のソロLPを気に入ってくださり「方舟」という彼のオーディオルームに招待されたりもしました。
長岡さんからの情報で聴いたノンサッチの「Animals of Africa Sounds of the Jungle, Plain & Bush」(nonesuch H-72056)というLPにはビックリしました。アフリカの動物たちの鳴き声の録音です。当時、聴きはじめていたヨーロッパのインプロビゼーションの音に似ていました。
何年か前のミュージックアクションフェスティバルで、フランスの若い演奏家が、最新の音響機器を駆使して川の水の流れや、鳥の声など自然音を出していました。締め切ったコンサートホールでした。外はカラッと晴れた良いお天気。外に出て、10分も歩けば、自然の音がいくらでもありました。
若尾祐・久美さんのやっているmesosticsに2枚のCDが扱われています。pulse of the planet (mescd-1001) は虫や動物の音、自然現象の音、宇宙の音がはいっていますし、bahia(mescd-1002)には、ブラジル・バイーアのサウンドスケープが収まっています。両方とも好きです。iTunesでシャッフルにしていてこれらの音がでてくるとギョッとします。
土方巽さんの舞踏は「売れる」ことを拒んでいたのではないか、という気がします。もっと言えば、売れる・売れないという次元を越えていた、「買えるものなら、買ってみろ!」という思いさえあったのではないでしょうか。商業主義の中では正反対のような「汚さ・病気・いかがわしさ」を前面に出す。エンターテイメントではなく、捧げ物としての側面を大事にすると自然にそうなっていったのでしょうか。「人生そのものが即興なのだから、わざわざ舞台で即興をする必要はない」と言っていたそうです。(一方、エンターテイメントの映画にも出演して怪奇さを発揮したり、ショー劇場「将軍」を経営したりしたのは、彼の大きさでしょう。)
ヨーロッパでは舞踏をコンテンポラリー・ダンスの中の一ジャンルとして扱っているように見えますが,根本的なところで違うのではないかと思います。そこを徹底したのが土方さんだったと今にして思います。
